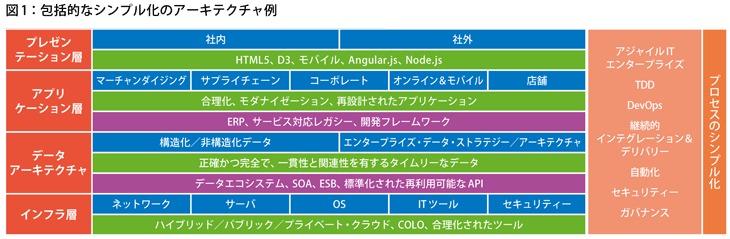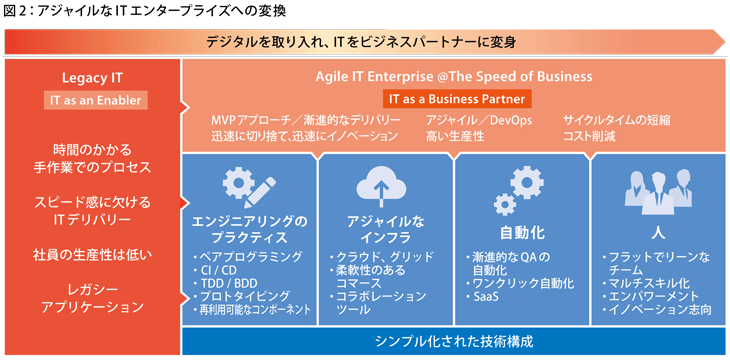目次
目次
ITのシンプル化で企業のデジタルが進化する
デジタル革命により、消費者の購買に対する期待は大きく変わりました。技術を使いこなし、購買の判断に必要な情報を即座に手に入れられるようになった消費者は、好きな時間に好きな場所で、自分に都合が良いようにサービスを受けることを期待しています。加えて、初めての完全なモバイル世代とされるZ世代※が消費者として市場に仲間入りしてきたことが、この傾向に一層拍車をかけています。このように技術とともに消費者の期待が進化し続ける中、小売業界は過去50年に経験したよりもはるかに大きな変化を、今後5年の間に経験すると予想されています。
こうした環境下でオムニチャネルの重要性はかつてないほどに高まっています。小売業者は、ミレニアル世代(*)やZ世代の消費者、つまりはオムニチャネルを当然のサービスとして期待する消費者への対応を迫られるでしょう。さらにオムニチャネルだけでなく、新たな技術やイノベーションを通じてビジネスモデルを常につくり変えていくという、大きなプレッシャーにさらされることになります。
そのプレッシャーを乗り越える優れた手段の一つが、Simplification(シンプル化)されたIT環境です。規模の大小を問わずすべての小売業者にとって、シンプル化は機敏な対応能力を獲得し、オンライン型の新たな競合相手に対抗していくためのカギとなります。ITをシンプル化することで、小売業者はアジャイル開発やデリバリーシステム、デジタル化社会を前提としたオペレーション、運用費用の低減などの恩恵を容易に受けられるようになり、市場の変化への迅速な対応が可能になります。
*ミレニアル世代/Z世代:海外では1980〜1995年生まれをミレニアル世代、1995年以降の生まれをZ世代と名付けている(年代は諸説あり)。いずれも物心がつく頃にはITの恩恵を受けていたデジタルネイティブで、米国では両者を合わせて人口の50%以上を占め、市場の重要なターゲットとなっている。
シンプル化が未来志向の企業を築く
合併や買収の増加、統合・標準化されていないシステムやルール、ペースの速い外部環境の変化などにより、小売企業のIT環境は複雑さを増すばかりです。一方で、既存の小売企業の多くは、融通が利かず費用もかかる頑強なレガシー環境でコア業務システムを運用しています。結果として、複数の技術やプラットフォーム、インフラによって構成される非常に異質で複雑なIT環境が構築されてしまい、企業が四苦八苦するケースがよく見られます。また、この複雑さが足かせとなり、将来を見据えた準備にも影響が出ています。
タタコンサルタンシーサービシズ(TCS)が注目するデジタルファイブフォースがビジネスモデルを大きく変え、新たな機会を生み出す中、レガシー環境を抱えたままの企業はビジネスニーズに応えるべき自社の能力にギャップを感じ始めています。こうしたギャップを放置すれば、小売業界で進む変化の度合いに比例してアーキテクチャやインフラ、プロセス、ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンスのモダナイゼーションされた環境がますます洗練され、そのズレはさらに広がってしまうでしょう。
顧客の期待やビジネスの需要に遅れずに対応していくには、複雑なIT環境を管理し、拡張性や俊敏性の獲得を容易にする「シンプル化」に着手することが必要です。具体的には、次のようなことを行います。
- アプリケーション、システム、データセンターの統合・合理化
- レガシーモダナイゼーション
- 運用環境の統一
- クラウドやオープンソースの導入
- 自動化
- ツールの合理化
続いて、企業に強固なデジタル基盤を築くシンプル化プロジェクトの主立った要素について説明していきます。
包括的な視点とアーキテクチャからアプローチする
レガシー環境で何らかの限界に直面したとき、回避策やパッチでしのごうとするケースがよく見受けられます。しかし、これでは技術スタック内の個々のレイヤー間、あるいは同じレイヤー内のアプリケーション間に非互換性を生じさせてしまいます。さらに、レガシー環境では多数のレイヤーが密接に絡み合っており、最新の技術を導入するに当たってシステムを刷新するような大きな負担が掛かることも珍しくありません。つまり技術スタック全体やそのプロセスに、複雑さの要因が存在しているのです。そのため包括的な視点と、アーキテクチャの観点から技術構成やプロセスを再設計するシンプル化の考え方が不可欠となります。図1は、そうした包括的なシンプル化アプローチの概要をまとめたものです。
アプリケーションポートフォリオを合理化する
米国の大手小売企業はこの手法によりメインフレームのメモリ使用量を圧縮し、マーチャンダイジングやサプライチェーンを含むコア業務システムのモダナイゼーションに成功しました。そのアーキテクチャには、レスポンスの良いフロントエンド、複数のソフトウエアを連携させやすく設計した「RESTful」なサービスレイヤー、さらにウェブ、モバイル、サービスプロバイダーで共通して利用可能なAPIが含まれています。
プロジェクトでは、まずポートフォリオの体系的な評価を通じて、アプリケーションを洗い出して、関連するビジネスプロセスへマッピングをした上、最善のモダナイゼーション戦略を取り入れたロードマップの策定を行いました。その結果、この企業は豊かなユーザーエクスペリエンスを提供しつつ、オムニチャネルをシームレスに統合することに成功しました。
この手法によりポートフォリオを見直してアプリケーションのボリュームを30%減らすとともに、店舗スタッフの労力を20%軽減してより価値の高い接客サービスに振り分けることができ、さらに約15%のコスト削減も実現しました。
インフラをクラウドにマイグレーションする
アプリケーションと並行してインフラの有効性をコスト、利用状況、パフォーマンス、可用性、アラインメントなどの観点から評価することも重要です。仮想化やグリッドコンピューティングの導入、ストレージの最適化、ハイブリッドクラウドモデルへのマイグレーションにより、パフォーマンスの向上や大幅なコスト節減を実現できます。柔軟性のあるアーキテクチャはオンデマンドの実験を低コストに抑え、結果的に企業ITの俊敏性も促進します。インフラをクラウドにマイグレーションすることにより、ヨーロッパの大手企業は新たな製品やエクスペリエンスのサービスインまでの期間を短縮するとともに、俊敏性、サービスの拡張性、エンドユーザーエクスペリエンスを向上できました。また、インフラ単体の性能向上にとどまらず、災害復旧体制の整備やTCOの30%削減にも成功しました。
統一されたデータアーキテクチャを構築する
先見の明のある小売企業は、データを的確に活用した意思決定により、常に競合他社の先を行くことができます。そのために彼らのような企業が主眼を置いているのが、よりシンプルで先を見越した企業情報管理(EIM)を実現できる、統一されたデータアーキテクチャです。リアルタイムに意思決定するには、構造化データおよび半構造化データをさまざまなソースから収集する必要がありますが、統一されていないデータアーキテクチャでは、企業内データを利用しやすい形でデータベースに書き出すETL処理の混乱を生んだり、データ不足から生まれた複数の「真実」の間で立ち往生してしまい、競合他社に遅れを取るばかりです。このようにデータ戦略(ビッグデータ戦略)の策定はシンプル化実現の非常に重要なポイントと言えるでしょう。
プロセスをシンプル化する
シンプル化された技術アーキテクチャに加え、俊敏性を可能にするITプロセスやプラクティスも重要です。ITプロセスを評価することは、アジャイル型開発プラクティスの実現につながります。継続的インテグレーション(CI)あるいは継続的デリバリー(CD)の活用、プロトタイピング、再利用可能なコンポーネントやAPI、開発担当者と運用担当者が連携する開発手法DevOpsなどのほか、「automation-as-a-culture」「innovation-as-a-culture」(自動化やイノベーションを組織全体で恒常的に実践すること)といったプラクティスを取り入れることも、ITデリバリーのケイパビリティを大きく前進させることにつながります。
図2は「エンジニアリングのプラクティス」「アジャイルインフラ」「自動化」「人」という四つの主要要素が、どのようにITを「Enabler」という単に業務を効率化するものでなく、「ビジネスパートナー」へと進化させるかを表しています。
先駆的な米国小売企業が成し遂げたのが、まさにこの進化でした。それまでのメインフレームを主体とするレガシーなIT構成を、継続的なインテグレーション、再利用可能なコンポーネントのライブラリ、アジャイル型開発のフレームワークといったアジャイルプラクティスに支えられた多層的なアーキテクチャへと変化させたのです。これにより、新しい製品やエクスペリエンスのサービスインまでの期間をわずか15分の1に短縮し、同時に顧客満足度も向上させることができました。
シンプル化プロジェクトを成功に導く五つのプラクティス
これまで説明した通り、企業に大きな可能性をもたらすシンプル化を成功させるには、体系立った手法による計画と実行が必要です。まずは詳細な評価を行い、短期的・長期的な計画を導き出すことから始めます。実用的で具体性のある導入ロードマップを策定し、実行に向けたプロジェクト管理のガイドラインを適用しましょう。
シンプル化プロジェクト推進のカギとなるのは「Execution Excellence」(実行力)です。加えて、自動化によるリスク軽減や導入コスト削減を見据えながら、しっかりとしたガバナンスや変更管理プロセスに沿ってプロジェクトを進行させることが重要です。
小売企業におけるシンプル化プロジェクトを成功させるための、五つのベストプラクティスをご紹介します。
- 長期的なビジョンを持つ:目指すべきITアーキテクチャは、企業の長期的な戦略を支え、かつ変化に対応できる柔軟性を備えたものでなければなりません。
- エグゼクティブスポンサーを置く:全社的に取り組むに当たっては、ビジネスの現場がリーダーシップを取り、プロジェクトの最終的な権限を持つエグゼクティブスポンサーがIT変革プロジェクトを支える、という形が理想的です。
- 包括的なアプローチを適用する:アプリケーション、プロセス、インフラといった全ての要素をシンプル化の目的に沿うように連携させ、同時にシンプル化させる必要があります。
- 早期に投資コストを回収し、次のプロジェクト費用を捻出する:迅速に投資対効果を期待できる分野から優先的に取り組むのも効率的な方法です。例えば、ユーザーエクスペリエンスや生産性の向上、スピーディーな意思決定を助けるリアルタイムでの情報の入手、高度なプラットフォームやインフラの設置などが該当します。こうした「低きに育っている果実」を収穫して節減できた費用を、他のシンプル化プロジェクトに回すと良いでしょう。
- タイムリーなコミュニケーションを促す:組織内で縦と横のコミュニケーションが取れていることが重要です。レポーティングのダッシュボードを設置するなど、経営上層部がIT変革を効果的に監視できるような工夫も有効です。
シンプル化のメリット
効果的なシンプル化プロジェクトは、小売企業をよりスピーディーで適応力の高い組織に変革し、それによりデジタルをはじめとする破壊的な技術を通じた継続的な革新を促進します。さらに、以下のようなメリットも期待できます。
- サービスインまでの期間が短縮され、社内ITサービスのよりスピーディーな提供や展開が可能に。
- アジャイル開発プロセスやクラウドインフラの活用により、デジタルイノベーションのスピードアップやアイデアの迅速な検討が可能に。
- より統合されたオムニチャンネルや、リアルタイムでパーソナライズされたデジタル対応により、カスタマーエクスペリエンスが向上。
- データをリアルタイムで捕捉・分析できる仕組みにすることで、データに基づくよりスピーディーな意思決定が可能に。
- イベント駆動型のプラグアンドプレイのフレームワークにより、破壊的な技術に対応可能な、将来を見据えた設計にすることで、アーキテクチャの柔軟性が向上。
- レガシーモダナイゼーションや、ソフトウエア/ハードウエアのライセンス費用を抑えるオープンソース技術の活用により、大幅なコスト節減が期待できる。
- アプリケーション、アーキテクチャ、インフラ、プロセスをモダナイゼーションすることで、IT管理や運用効率が向上。
著者
Aashish Chandra
タタコンサルタンシーサービシズ
小売・消費財業界テクノロジーグローバルヘッド
2015年3月TCS入社、現在はシンプル化プラクティスの推進に取り組んでいる。TCS入社以前はシアーズ・ホールディングス社(NASDAQ: SHLD)の副社長としてアプリケーション・モダナイゼーションを率いていたほか、共同創業者としてビッグデータのベンチャー企業MetaScaleも立ち上げている。
現在、サンフランシスコ・ベイエリアにある技術系ベンチャー事業の顧問、ならびにインド商科大学院の客員教授も務め、米国シリコンバレーを拠点に活躍している。
※掲載内容は2016年5月時点のものです。